市民の皆様へ
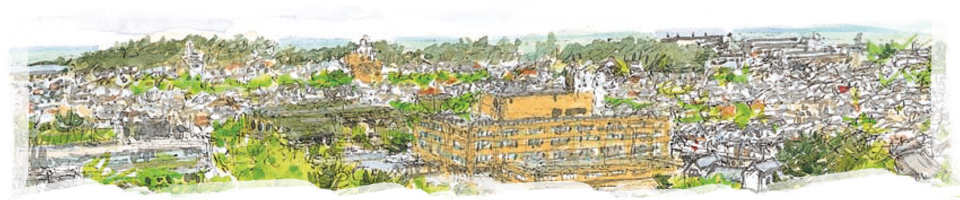
新しいドライアイ点眼薬について
臼井 知聡
(東区 あきば眼科クリニック)
私が新潟大学を卒業した昭和62年に発売された『イラスト眼科』という教科書(初版)にはドライアイという言葉は載っていません。ところが今ではドライアイという言葉は広く知られるようになり、それに関するテレビ番組や新聞・雑誌記事なども数多く見受けられます。一般には「かわきめ」と呼ばれますが、そのメカニズムは複雑です。涙液は水層、油層、ムチン層に分かれ、涙液の質的・量的異常に伴い、角結膜上皮障害が生じます。その症状には目の乾燥感だけでなく、目の痛み、異物感、目の赤み、まぶしさ、目のかすみ、目の重たい感じなどが挙げられます。症状の共通点は「目を開けているのがつらい、閉じていた方が楽」と言えます。パソコン・携帯電話の普及、コンタクトレンズやエアコンの利用などによりドライアイ患者は増えています。
ドライアイの治療薬として人工涙液の点眼があります。これは涙の水分量を補い、目の表面の涙液の安定性を高めることを目的とした目薬です。平成7年に国内で精製ヒアルロン酸ナトリウム点眼液が初めて発売されました。ヒアルロン酸は粘り気を持っており、人工涙液よりも高い安定性をもたらす目薬です。発売当初は0.1%の濃度のものしかありませんでしたが、現在では0.3%のものもあり、症状に合わせて使い分けることが可能です。
近年2種類の新しい点眼薬が発売されました。ひとつはジクアホソルナトリウムを含む目薬です。これは結膜上皮細胞に水分を分泌させて目の表面の水分を増やすと同時に、結膜の杯細胞でのムチン分泌を促進させます。もうひとつはレバミピド点眼薬です。レバミピドは胃粘液(ムチン)増加作用を有していることから、眼ムチンに対する作用について検討され開発されました。従来のドライアイ治療は涙液を補うことがメインでしたが、ムチン産生促進剤である新たな点眼薬が開発されたことで、眼表面の粘膜を修復し、ムチン産生を増加させることで、涙液の安定性を保ち、ドライアイによる角結膜上皮障害と自覚症状が改善すると考えられます。
「目を開けているのがつらい、閉じていた方が楽」という患者さんは多いと思われます。「疲れがたまっているから」「年のせいだから」などとあきらめる前に眼科医に一度相談されることをおすすめします。
(2013.9.10)
(2013.09.10)
