市民の皆様へ
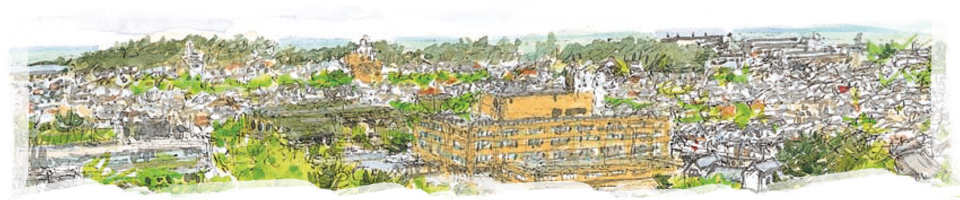
精神医療に対する誤解と偏見
坂井 正晴
精神科医療機関への受診患者数は最近急激に増加しています。これはストレス社会を反映した現象であり、精神科への受診に対する抵抗感が減ってきたためと思われます。しかし今でも精神疾患や精神医療に対する偏見と誤解は根強いものがあります。例えば「精神障害は治らない」「精神障害者は何をするかわからなくて怖い」「精神安定剤や睡眠薬は服用すると依存性があってやめられなくなる。服薬を続けていると将来認知症になる」「精神疾患は心が弱いわがままな人の病気だ」など数えあげたらきりがありません。これらはまったく根拠が無いものです。一般に重症な精神疾患と考えられる統合失調症であっても、適切な治療で改善し社会復帰されている患者さんは数多くいますし、精神障害者の犯罪を犯す割合は一般の人に比べけっして高くありません。病気の再発を予防するために長期間の服薬が必要な人がいることは間違いありませんが、適切な服薬を続けているなら、依存状態になることはまれですし、人格を変えたりマインドコントロールするような作用はありません。認知症につながることもありません。全ての人が心の病気になる可能性があり、決して特別な人だけが病気になるわけではありません。誤解と偏見が適切な治療と社会復帰をさまたげ、患者と家族に苦痛を与える要因になっていますし、本来持っている能力を発揮できなくなることは、社会にとっても大きな損失につながります。正しい知識を持つことは、自分自身の、身近な人の心の健康を保ち、必要なときに適切な治療を受けることに役立ちます。精神保健福祉センター、保健所、当事者の会(患者自身の会)、家族会など様々な機関や団体が講習会や交流会を開いています。一度参加されてみるのも良い経験になるのではないでしょうか。講習会や交流会の情報は「市報にいがた」や新聞にも掲載されますので、参考にしてください。
(2007.03.29)
